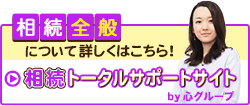何らかの犯罪の嫌疑をかけられた場合、逮捕されてしまうことがあります。
もっとも、犯罪の嫌疑があったとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕しておかないと、逃亡してしまう可能性や、証拠を隠滅してしまうような可能性がある場合に、逮捕がなされます。
逮捕されると、留置所というところに入れられ、警察からの取り調べを受けることになります。
逮捕から48時間以内に、検察官に事件の内容が知らされ、勾留請求するかどうかが決まります。
検察官が、勾留請求をしたいと考えれば、裁判官に対し、勾留請求を行い、裁判官が認めれば、そこから10日間、身柄拘束されることになります。
さらに、検察官が、勾留を延長する必要があると判断した場合、最大で10日間、勾留が延長されます。
このように、逮捕・交流がなされると、長期間、留置所に拘束され、その間、学校に行くことや仕事に行くことはできず、さらに外部の人と会うことも困難な状態になります。
仮に、無断で20日も仕事を休めば、それだけで職を失うことにもなりかねません。
そこで、弁護士は、身柄拘束が長引かないような弁護活動をすることになります。
まず、逮捕後、検察官に事件の引き継ぎがなされた段階で、勾留請求をしないように働きかけます。
勾留請求は、どのような場合でも認められるわけではなく、法律上の要件が定められています。
弁護士は、「今回は、逃亡のおそれはないし、証拠隠滅のおそれもない」といったことを、検察官に訴えます。
また、検察官が勾留請求をした場合、弁護士は、裁判官に対し、勾留請求を認めないよう働きかけていきます。
ただし、統計的は、たとえば2017年で勾留請求は約95%が認められているため、なかなか厳しい現実があります。
また、勾留が認められた後、弁護士は、勾留をやめて、すぐに身体拘束を解くように求めていきます。
勾留からの解放を求める行為を、法的には準抗告と呼びます。
勾留中であっても、弁護士は接見をすることができるので、事件の具体的な内容を聞くことができます。
そこで得た情報をもとに、今後の弁護方針を決めたり、あるいはご家族に連絡を取り、学校や職場へどのような説明をするかを検討します。
同時に、検察官が被疑者を裁判にかけることを検討している場合には、それをさせないための活動を行います。
たとえば、被疑者が犯罪事実を否認している場合は、それを証明するための証拠を集めますし、犯罪事実自体は認めている場合、被害者との示談をしていくことになります。