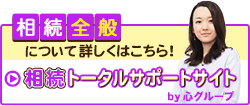ニュースなどでは、会社の破産について、破産ではなく、倒産という言葉が使われることが多いように思います。
しかし、裁判所での手続きでは、倒産という言葉はあまり使わず、普通に破産という言葉が使われますし、法律上、個人の破産と法人の破産は区別されていません。
もっとも、法人の破産は、個人の破産にはない特殊性があり、弁護士もそこに注意を払います。
まず、個人の破産と比較し、債務額が大きくなりがちで、数千万円から、数億円の債務があることも珍しくありません。
また、会社の代表者が連帯保証人になっていることが多いため、会社の破産を行う場合、代表者も一緒に破産することが多いです。
さらに、個人の破産であれば、債権者の多くは消費者金融やクレジットカード会社ですが、会社の破産の場合、債権者は多種多様です。
たとえば、飲食店を経営している会社であれば、食材の仕入れ業者などにも未払いがあったりしますし、従業員への給与が未払いであれば、従業員も債権者にあたります。
特に、従業員の方の扱いは、とても慎重な検討が必要です。
破産に伴い解雇するのであれば、原則として、解雇予告手当というものの支払わねばならず、その原資の確保に気を使いますし、なるべく給与も全額支払えるようにしなければなりません。
仮に、給与を全額支払えなかった場合、未払い給与の一部を立て替えてもらえる制度があるため、その活用も必要ですが、期間制限があるので、迅速な対応が求められます。
また、会社が破産をする場合、事前に弁護士に相談し、色々な準備をしてから、破産する旨の通知を関係者に送ることが多いですが、その途中で、従業員や取引先などに破産のことを知られると、大混乱を招くことになるため、情報漏洩にも気をつけなければなりません。