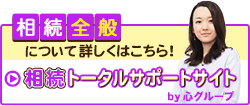刑事事件の一審で、有罪判決が出た場合、弁護士(弁護人)としては、高等裁判所に不服申し立てをすることを検討しなければなりません。
この不服申し立てを控訴といいます。
弁護士(弁護人)は、控訴審で、一審判決のおかしい部分を、徹底的に追及することになります。
たとえば、コンビニ強盗事件おいて、①犯人は黒いジャージ姿であった、②犯人は、身長が170センチだった、③犯人は、包丁を使って店員を脅したという事実関係があったとします。
仮に、1審判決が、①被告人の家から、黒いジャージが発見された、②被告人の身長は170センチである、③被告人の家から包丁が発見された、という点を根拠に、被告人が有罪であるという判決を書いた場合は、どのような追及が考えられるでしょうか。
まず、上記①~③の点から、被告人が犯人であると断定することは困難であると主張することになるでしょう。
つまり、①黒いジャージは珍しいものではないし、②身長170センチの人はたくさんおり、③どの家にも包丁くらいあって当然という主張をすることが想定されます。
このように、事実関係で争いがあるようなケースでは、論理法則や経験則などを駆使して、1審判決に対し、反論をしていかなければなりません。
他方で、事実関係を争っていなくても、量刑が不当であるという主張もあり得ます。
たとえば、今までの裁判の相場観からすれば、懲役1年程度が妥当であるというケースにもかかわらず、懲役10年という判決が出てしまった場合、その量刑の不当性を主張することになります。