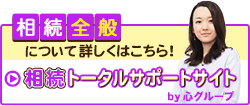検察官が起訴したということは、いよいよ刑事裁判が始まるということを意味します。
検察庁は、負ける戦いはしない組織と言われることがあるほど、有罪にできる自信がある時だけ、起訴をする傾向にあります。
そのため、弁護人としては、起訴後の弁護活動も、非常に重要なものになります。
まず、起訴された場合は、起訴状を入手する必要があります。
起訴状には、被告人が、どのような行為が、どのような罪になるのかについて、検察官の主張が記載されています。
起訴状には、証拠がついていないため、起訴状を読んだら、まずは検察官がどのような証拠で立証をしようとしているのかを予測する必要があります。
たとえば、飲食店の中で暴行事件が起きたという場合であれば、その飲食店の店員の証言が重視されるかもしれませんし、店内の防犯カメラの映像が証拠として提出されるかもしれません。
他方、覚せい剤などの薬物事件では、被告人の体内から、薬物が検出されたり、被告人の家から薬物や薬物接種のための器具が発見されているかもしれません。
この時点で、事件の見通しを立てるのですが、実際の裁判が始まる前に、弁護人は、検察官が裁判所に提出する予定の証拠を、閲覧・謄写することができます。
弁護人は、当該証拠を見て、検察官の立証構造を把握します。
その上で、公判で、どのような主張を行うかを決めていきます。
まず、最初に決めることは、起訴状に記載された事実を認めるかどうかです。
証拠上、犯罪事実があったことが明らかで、被告人もそれを認めている場合は、犯罪事実については争わず、情状面での立証をしていくことになります。
他方で、検察官が提出した証拠では、犯罪事実が証明できていないような場合や、被告人が、犯罪事実を争っている場合は、検察官の立証構造を崩すための方針を固めることになります。
特に、犯罪事実を争う場合は、弁護人側も、積極的な証拠収集が必要になります。
まず、検察官側は、持っている全ての証拠を、開示しているわけではありません。
有罪の立証に必要な証拠を厳選して、裁判所に提出しようとしています。
しかし、検察官が提出していない証拠には、被告人にとって有利な証拠が存在する可能性があります。
そこで、できるだけ証拠を集めるために、弁護人は、検察官に、証拠の開示請求を行っていきます。
検察官が任意に証拠開示に応じる場合は、それでいいのですが、証拠開示に応じない場合もあります。
その場合は、裁判所に対し、証拠開示命令の申立を行い、積極的に証拠を集めていくことになります。
こういった、起訴前の攻防についても、弁護士としての力量が問われます。