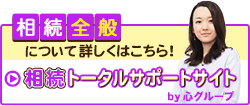人が死亡すると、法律上は相続が発生したことになります。
相続が発生すると、法的には様々な現象が起きます。
たとえば、お父さんが亡くなって、相続人が長男と二男という例を考えてみます。
お父さんが亡くなると、お父さんは「財産を所有する権利」を失います。
そのため、お父さんが生前に自宅の不動産を所有していたり、預貯金口座を持っていたとしても、お父さんが亡くなると同時に、お父さんのものではなくなります。
その代わり、お父さんが所有していた財産の権利は、相続人の長男と二男に受け継がれることになります。
では、ここで疑問になるのが、「いつ人は死んだことになるのか」という点です。
もちろん、多くの場合は、生物学上の死をもって、死亡したということになりますし、弁護士もその前提で実務を行っています。
しかし、「生物学上の死を確認できない限り、人は死亡しない」ということになると、困ったことが起きるケースがあります。
たとえば、遭難などで行方不明になっている方です。
行方不明になり、住民票も存在しないような場合だと、その人が生きているのかどうか判断がつきません。
行方不明の方の生物学上の死を確認することは、非常に困難です。
それにもかかわらず、行方不明の方がずっと生きているということにすると、仮にその方が戸籍上200歳になっても、法律上は存命ということになります。
そこで、「一定の条件を満たした場合、その人は法律上死亡したことにする」、という法律があります。
まず、特定の方が行方不明になり、7年間生死が不明の場合、裁判所に「この人は亡くなったということにして欲しい」という申立てができます。
また、戦争や船舶の沈没など、命の危険があるような現場にいた方については、1年間生死が不明の場合、同様の手続きが可能になります。
もっとも、これらの手続きで人が亡くなっても、それはあくまで、「法的に亡くなったことにする」というだけなので、「後になって存命であることが分かった」という場合は、裁判所に対し「法律上死亡したことを取り消して欲しい」という申し出ができます。
また、最近では、脳死状態を人の死亡と考えるかどうかについて、色々な議論があります。
「臓器の移植に関する法律」では、一定の条件を満たした場合、脳死状態の方から、臓器を摘出することが認められています。
生きている人から臓器を取り出すと、殺人罪に問われかねないため、臓器移植の場面に限って言えば、脳死状態を人の死と考えていると言えるでしょう。