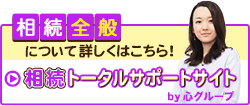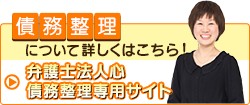裁判所に自己破産の申し立てをした場合、裁判所から、「反省文を書くように」という指示が出されることがあります。
では、反省文の提出を求められた場合、どのようなことを記載すればよいのでしょうか。
それを検討するにあたっては、まず、裁判所が反省文の提出を求めている趣旨を明らかにする必要があります。
自己破産手続きは、そう何度も繰り返すことができる手続きではありませんので、裁判所としては、二度と破産手続きをしなくても済むように、破産する方に対し、生活の再建を望んでいます。
そのため、どういった理由で自己破産をするにいたり、どういう点を改善すれば、もう破産手続きを取らなくてよくなるのかという点を、ゆっくり考える機会を与えるという意味で、反省文の作成を求めています。
以上が、裁判所が反省文を求める趣旨ですので、まずは、自己破産をするにいたった原因と対策を記載する必要があります。
たとえば、借金が増えた理由がギャンブルであれば、なぜギャンブルをするようになったのか、今後はギャンブルをしないために、どのような対策を講じるのかといった記載をすることになります。
他方、趣味にお金をかけてしまったり、食費や家賃などが収入に見合わないものであったりしたことが原因で借金が増えてしまった場合は、しっかりと家計簿をつけた上で、収入の範囲内で生活できることを示していくといった対策が必要になります。
とはいえ、多くの場合、弁護士が反省文の書き方についてご説明することになりますので、破産する方が、いちから考えて作成しなければならないというわけではありません。